営業電話はこう断る!|失礼なく断るフレーズ・相手別の対応方法・断ってはいけないケースも解説
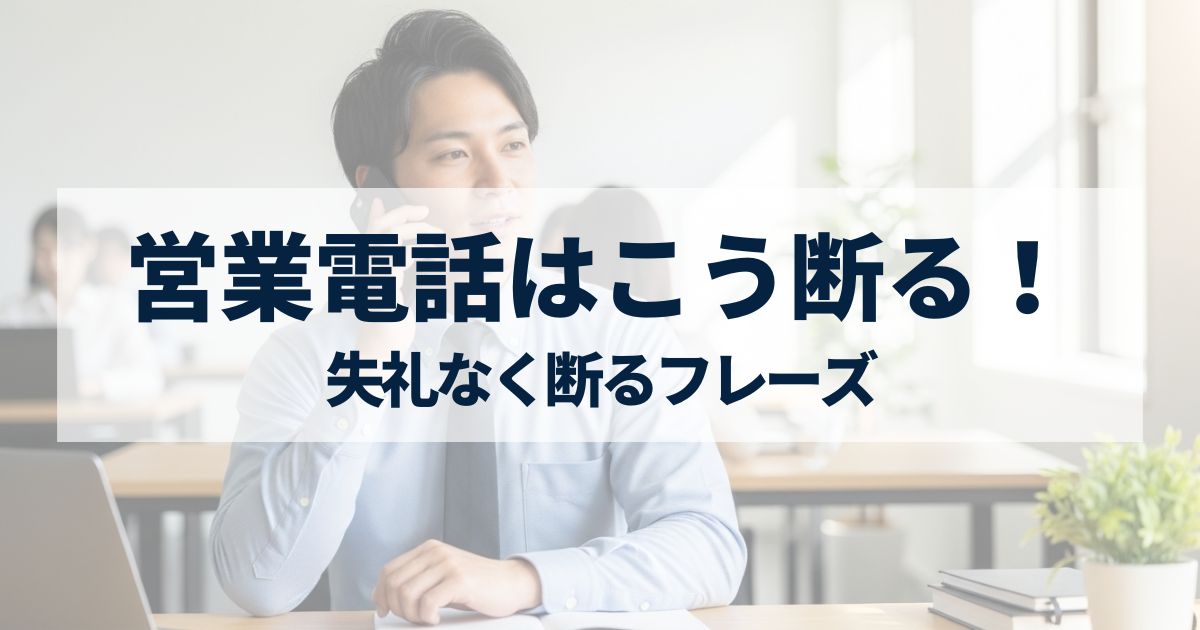
日常的にかかってくる営業電話。「いまお時間よろしいでしょうか?」と始まるその一言に、どう返せば良いか迷う人は多いのではないでしょうか。
保険・不動産・通信回線・人材紹介・広告代理店など、さまざまな業種から営業電話はかかってきます。しかし、すべてを聞いていては時間がいくらあっても足りません。かといって、強く断ると「失礼にあたるのでは?」と気になる方もいるでしょう。
この記事では、営業電話を「丁寧に、でもきっぱりと」断る方法を、具体的なフレーズ付きで解説します。また、相手の立場別の対応方法や、断ってはいけないケースも紹介します。
営業電話を断るときの基本マナー
1. 最初の3秒で“態度”を決める
営業電話がかかってきたとき、「あいまいな対応」をしてしまうと、相手は“チャンスあり”と感じて話を長引かせます。そのため、冒頭で「興味がない」「対応できない」ことを明確に伝えるのが大切です。
✓ 悪い例
- 「ちょっと考えておきます」
- 「今は忙しいので、またあとで」
これらは“将来的には可能性がある”と受け取られてしまい、再度かかってくる原因になります。
✓ 良い例
- 「申し訳ありませんが、必要ございません」
- 「弊社ではすでに対応済みですので、今回は結構です」
短く・丁寧に・明確に。これが営業電話対応の基本です。
2. 相手を否定せずに“自分の都合”を伝える
営業相手を直接否定すると、相手も反発してきます。「そんなに悪い話ではありませんよ」などと食い下がられることも。
そこで有効なのが、“自分の事情”を理由にする断り方です。
- 「社内ルールで新規取引をしておりません」
- 「上長の方針で対応ができません」
- 「別の会社で契約しており、今後も変更予定はありません」
このように「あなたではなく、こちらの事情」と伝えることで、角を立てずに断れます。
3. 感情的にならず、あくまでビジネスライクに
営業電話は、相手も仕事として行っています。必要以上にイライラしたり、感情的に対応したりすると、自分の印象を悪くしてしまいます。
重要なのは「一線を引く姿勢」です。淡々と、丁寧に、ビジネス的な言葉づかいで断ることで、相手も早めに引き下がります。
【ケース別】営業電話を断るフレーズ集
ここでは、よくある営業電話の種類別に、失礼のない断りフレーズを紹介します。そのまま使える言い回しとして、実践的な表現を中心にまとめました。
1. 不動産・投資・マンション販売の営業電話
このタイプは「資産運用」「節税」などを切り口にアプローチしてくるのが特徴。断っても「将来のために」「話を聞くだけでも」と粘るケースが多いです。
おすすめの断り方:
- 「申し訳ありませんが、投資や不動産には関心がございません。」
- 「お話は理解いたしましたが、現時点で検討の予定はございません。」
- 「将来的にもその分野に取り組む予定はありませんので、お気遣いなくお願いいたします。」
ポイントは、“現時点で”ではなく“今後も”と明言すること。この一言で、再アプローチを防ぐ効果があります。
2. 保険・金融商品の営業電話
金融・保険系は、顧客データをもとに電話してくるケースが多く、断っても再連絡されることがあるジャンルです。
おすすめの断り方:
- 「すでに契約先が決まっておりまして、今後も変更の予定はございません。」
- 「担当の保険会社がありますので、他社の方とはお取引しておりません。」
- 「今後のご提案についてはすべて担当代理店を通すことになっております。」
ここでは「既存契約がある」「社内ルール」といった外的な理由を添えることで、強く切り返されるリスクを下げられます。
3. 通信回線・電力・インフラ関連の営業電話
「通信費を安くできます」「電力会社の見直し」などの営業が多いタイプ。とくに法人宛の電話は頻繁です。
おすすめの断り方:
- 「すでに別の代理店様で契約しており、変更予定はございません。」
- 「会社の方針で新規のお取引は行っておりません。」
- 「担当部署が異なりますので、今後はそちらにおかけいただけますか?」
ここでは「担当部署」を理由に断るのも効果的です。担当者を明示せずにやんわり回避することで、社内混乱を避けられます。
4. 広告・Web制作・求人媒体などの営業電話
法人経営者や店舗オーナーに多いのがこのタイプ。「ホームページを見て電話しました」「求人広告を出しませんか?」とアプローチされるケースです。
おすすめの断り方:
- 「現在は他社様にお願いしておりますので、切り替えの予定はございません。」
- 「予算の都合上、今期は新規の広告出稿を行わない方針です。」
- 「すでに広告運用は内製化しております。」
このタイプは担当者を明確にせずに切り返すのがポイントです。「社内で決定済み」「今期は動かない」と伝えることで、粘られずに済みます。
5. 採用・人材紹介の営業電話
採用担当者や経営者に頻繁にかかってくる営業電話です。人材紹介会社や求人媒体、派遣会社などから「候補者を紹介したい」と言われるパターン。
おすすめの断り方:
- 「現在は自社採用で進めており、外部紹介は利用しておりません。」
- 「当面の採用計画がないため、ご提案は控えさせていただきます。」
- 「利用の際は公式サイトからお問合せいたしますので、今後のご案内は不要です。」
“今後連絡不要”をやんわり伝えておくことで、営業リストから除外される確率が高まります。
【相手別】営業電話への上手な対応方法
営業電話の相手にはさまざまな立場があり、誰からの連絡かによって対応方法を変えることで、よりスムーズに断れます。ここでは代表的なパターンを紹介します。
1. 法人宛て(会社・店舗にかかってくる場合)
法人宛ての営業電話では、「担当者不在」や「社内ルール」を活用するのが基本です。
対応フレーズ例:
- 「担当者が外出中のため、折り返しは不要です。」
- 「新規取引に関しては代表メールからのみ受け付けております。」
- 「社内方針で電話営業はすべてお断りしております。」
このように、個人判断ではなく会社ルールとして断ると、相手も無理に食い下がれません。特に小規模事業や店舗では、従業員が独断で断りづらいこともあるため、「経営者・管理者の方針で」と添えるとより効果的です。
2. 個人宛て(自宅・携帯にかかってくる場合)
個人向けの営業は、「明確な興味のなさ」と「今後の連絡拒否」をはっきり伝えるのが大切です。
対応フレーズ例:
- 「興味がありませんので、今後のご連絡は不要です。」
- 「個人情報の削除をお願いいたします。」
- 「必要な際はこちらからご連絡いたします。」
相手がしつこい場合は、「電話番号を登録しておきます」と伝えるのも抑止力になります。あくまで冷静に、毅然と対応することがポイントです。
3. 名刺交換した営業担当からのフォロー電話
展示会・イベント・セミナーなどで名刺を交換した相手からの電話は、「完全な迷惑電話」ではありません。将来的な関係を残す可能性もあるため、やんわり断るのが望ましいです。
対応フレーズ例:
- 「先日はありがとうございました。現在は別案件で手一杯のため、今回は見送らせてください。」
- 「ご提案内容は理解しました。タイミングが合えば、こちらからご連絡いたします。」
- 「今後の情報はメールでいただければ幸いです。」
対面で接点を持った営業相手は、再会することもあります。“断る=縁を切る”ではなく、“保留”の形で終えるのが大人の対応です。
4. 既存の取引先・担当者からの営業電話
すでに関係のある会社の担当者が、別サービスを提案してくる場合もあります。完全に断ると角が立つため、「今回は保留」「来期検討」など、やわらかく表現するのが効果的です。
対応フレーズ例:
- 「現時点では必要ありませんが、次回の契約更新時に検討させてください。」
- 「ご提案ありがとうございます。社内で共有したうえで、必要な場合はこちらからご連絡します。」
- 「来期の予算検討時に改めてお話できればと思います。」
既存取引先への対応は、関係維持を優先しましょう。将来的なビジネスチャンスにつながる可能性もあるため、感情的な対応は避けるのが無難です。
【NG例】やってはいけない断り方
営業電話を受けるときに避けるべき対応もあります。丁寧に断るつもりが、逆に長引かせてしまうこともあるため注意が必要です。
NG①:「ちょっと考えておきます」「また今度」
この表現は、相手にとって「脈あり」サインに聞こえます。営業担当者は“少しでも興味を示した”と判断して、再度連絡してきます。
→ 対策:
「必要ありません」「検討予定はありません」と、はっきり言い切りましょう。
NG②:「担当者がいません」だけで終わる
担当者不在を理由にするときは、“今後の連絡先を制限する一言”を加えることが重要です。そうしないと、「では何時にいらっしゃいますか?」と再度食い下がられます。
→ 対策:
「担当者は外出中で、折り返しは不要です」「連絡は代表メールにお願いします」など、次の行動を封じる言葉を添えましょう。
NG③:感情的に怒鳴る・切る
不快な営業電話であっても、怒鳴ったり、強引に切ったりするとトラブルのもとになります。場合によっては、「対応が悪い」とクレームを逆に入れられることも。
→ 対策:
淡々と「結構です」「失礼します」と伝え、会話を打ち切るのがベストです。
NG④:「ほかの人に任せてます」など曖昧な表現
「自分では判断できません」「別の担当が」などの曖昧な返答は、相手に“担当者を探そう”と思わせてしまいます。営業電話を完全に断りたいときは、「会社としてお取引しません」と明言する方が効果的です。
断ってはいけないケースもある?
すべての営業電話が“迷惑”というわけではありません。中には、あなたの利益につながる重要な連絡も含まれている場合があります。
ケース①:既存契約・サポートに関する連絡
たとえば、現在利用中のサービスや保険などの契約更新・不具合対応の電話は、営業ではなく重要な案内の可能性があります。内容を確認せずに切ってしまうと、トラブルにつながることも。
→ 対応ポイント:
- 「ご契約中のサービスに関するご連絡でしょうか?」
- 「サポートの件でしたら、担当部署におつなぎします」
営業かサポートかを一度確認してから対応しましょう。
ケース②:取引先の担当変更やお知らせ
既存の取引先からの担当変更・価格改定・契約条件見直しの電話もあります。これは営業ではなく「業務連絡」に近いものです。一方的に断ってしまうと、後々「伝達漏れ」が起きるおそれもあります。
→ 対応ポイント:
内容を一度聞き、「営業目的でなければ受け取る」姿勢を持つことが重要です。
ケース③:自社に関係する業界団体・行政関連の案内
まれに「商工会」「行政委託」などを名乗る電話もあります。一部は本物ですが、中には偽装営業もあるため注意が必要です。疑わしい場合は「担当部署」「正式文書の送付」を依頼しましょう。
営業電話を減らす・防ぐための実践対策
上手に断るだけでなく、そもそも営業電話がかかってこない仕組みを作ることも大切です。ここでは、個人・法人それぞれの立場でできる対策を紹介します。
1. 電話番号の管理を徹底する
営業電話の多くは、「名簿業者」や「公開情報」から番号を入手してかけてきます。そのため、不用意に電話番号を公開しないことが第一の防御策です。
実践ポイント:
- 名刺・SNS・ホームページなどに個人携帯番号を掲載しない
- 代表番号以外を問い合わせ窓口に使わない
- 会員登録時に「営業目的の利用を拒否する」チェックを入れる
特に法人では、「代表番号」と「営業窓口番号」を分けて運用すると、不要な営業を振り分けやすくなります。
2. 着信拒否や迷惑電話フィルタを活用
スマートフォンには、営業電話を自動で検知・ブロックするアプリや機能があります。代表的なものに以下があります。
- 迷惑電話ブロック(NTTドコモ・au・ソフトバンク)
- Google電話アプリの迷惑判定機能(Android)
- iPhoneの「不明な発信者を消音」設定
- スマート留守電やWhoscallなどのアプリ
これらを活用すれば、しつこい営業電話を自動で遮断できます。法人電話の場合も、PBX(ビジネスフォン)やクラウド電話で番号制限機能を使うのがおすすめです。
3. 「営業電話お断り」を明示する
法人や店舗の場合、ホームページや問い合わせフォームに以下のように記載しておくことで、一定の抑止効果があります。
※営業・勧誘・代理店募集などのお電話・メールはすべてお断りしております。
また、受付担当者向けに「営業電話の対応ルール」を共有しておくことも有効です。
例:
- 営業電話の内容を聞かずに「お断りします」で統一
- 再連絡希望には「代表メールをご案内」で対応
- 特定企業からの頻繁な営業はリスト管理して対応停止
組織全体でルールを徹底することで、営業電話を最小限に抑えられます。
4. 名簿削除を正式に依頼する
同じ業者から何度も電話がある場合は、「電話営業の停止・個人情報削除」を正式に依頼しましょう。
フレーズ例:
- 「個人情報保護法に基づき、私の連絡先を御社の営業リストから削除してください。」
- 「再度のご連絡はご遠慮願います。」
これで多くの業者は対応を控えます。悪質なケースでは、消費者センターや総務省への相談も検討しましょう。
どうしよう?困ったときは、消費者ホットライン188番にご相談を! | 政府広報オンライン
企業側での営業電話対策(法人向け)
企業代表宛に頻繁にかかる営業電話への対策も整理しておきます。
対策①:受付専用スクリプトを作る
受付担当者が迷わず対応できるよう、定型フレーズを社内共有しておくのが効果的です。
例:
- 「恐れ入りますが、営業目的のお電話はすべてお断りしております。」
- 「担当部署への取次ぎは行っておりません。」
- 「ご用件は代表メール宛にお願いいたします。」
この3ステップで、会話を長引かせず即終了できる体制を作れます。
対策②:代表番号をIVR(自動音声)にする
「○○の方は1を、営業の方は2を」などの音声ガイダンスを設けることで、営業電話を自動で切り分けることが可能です。多くの企業はこの仕組みで担当者が営業電話を受ける時間をゼロ化しています。
対策③:営業情報共有シートを作る
頻繁に営業をかけてくる会社の情報を一覧化し、受付・管理職・経営層で共有すると、「同じ会社に複数の部署が対応していた」などのムダを防げます。
まとめ|営業電話は「断り方」よりも「姿勢」で決まる
営業電話は避けられないものですが、対応の仕方次第で時間のロスもストレスも大きく減らせます。重要なのは、「感情ではなく、ルールと姿勢で断る」ことです。
丁寧で失礼のない断り方のポイント
- あいまいにせず、はっきり断る
→ 「必要ありません」「対応できません」と明確に伝える - 相手を否定せず、自分の都合を理由にする
→ 「社内ルールで」「担当がいません」など - 感情的にならず、冷静・簡潔に対応する
→ 「お忙しいところ失礼します」で締める - しつこい相手には法的ワードで牽制する
→ 「営業リストから削除をお願いします」
今後の営業電話対策
- 電話番号の公開を最小限に
- 着信拒否・迷惑電話アプリの活用
- 「営業お断り」明示と社内共有
- 名簿削除・通報による再発防止
営業電話は、正しく断れば恐れるものではありません。相手を立てつつ、こちらの立場も守る、そんな“スマートな断り方”を身につけておくことで、あなたの時間も、会社の生産性も、確実に守ることができます。